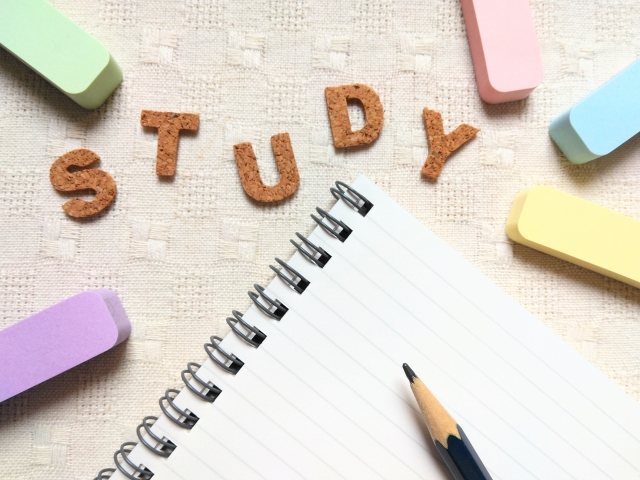第27回「子どもの心」研修会(前期)報告

研修会概要
- 日時:2025年5月10日(土)、11日(日)
- 会場:砂防会館別館利根(東京都千代田区)
- 開催方法:hybrid開催[現地又はLIVE配信視聴]
- 参加者:現地参加178名、WEB参加451名、計629名
- 研修会プログラム:第27回「子どもの心」研修会プログラム(PDF)
研修会を終えて
「SNS誹謗中傷の実態と求められる対策」では、インターネットが経済システムを大きく変え、ネット上での誹謗中傷がどのような背景で起こるかを解説していただき、その中で「アディクション・エコノミー」「フィルターバブル」「エコーチェンバー」の説明をいただいた。誹謗中傷は民主主義の危機であり、その対策として予防・対処・加害者にならないことは、子供に関わるものにとってとても大切な視点だと感じました。
「読み書き困難のある子どもたちへの支援 社会的解決を目指して」では、「読み書き困難」を抱えるご自身のお子さんとの体験を通し、実際にどのような困難がありその度に対どう処してきたか、そして現在の活動に至っているのか講演していただきました。講師のプログラムでとても特徴的なのは、「配慮要請の力を育てる」ということです。自分の弱みを明確に知り、それをエレガントに伝え、「配慮を要請」する。大学生のお子さんが活躍しているお話を聞き、大変明るい気分になりました。新しい視点をありがとうございます。
「6ヶ国育ちが体験した世界の教育の多様性」では、毎年転校を繰り返し戸惑いながらも講師がどのように過ごしていったのかを聞かせていただきました。体験を通し、それぞれの環境で自分が「サバイブ」していくには自分の軸と自分のキャラ(性格)を知り、創意・工夫を行い、違いを生かして武器とする。「個性」をもっと大切にすることの大事さを再認識しました。
「子育てのエビデンス」の講演で「子育てで何を育てるか?」ということに対し講師は、「アタッチメントという土台の上に非認知能力を育て、相乗効果として認知能力や年齢に応じた健康・体力を育む」ことについて御自身の研究を通し解説していただきました。アタッチメントの重要性を再認識させられ、非認知能力(セルフコントロール、モチベーション、共感力、レジリエンス)が高かった子どもの傾向を教えていただき、日々の臨床でも伝えていきたいと思いました。
「児童福祉の現場から」では、普段、児童相談所と関わる時に苦手感を持っている方には大変ためになる講演であったのではないかと思います。児童相談所の役割(できること、できないこと)、児童相談所に医療側が連絡する際のプレゼンテーションの仕方、都道府県の児相と中核市・特別区の児相の違い、など実際の臨床の場で非常に役に立つ内容でした。
「発達障害のある子どもの親に対するペアレントトレーニング」では、国内外のペアレントトレーニング(PT)の歴史と本邦でのPTの実際を解説していただいた。発達障害のある子どもの親は、ストレスが高いためPTにより育児ストレスを軽減させることが可能であり、発達障害の有無にかかわらず、PTによる支援は子どもたちの発達を促すことが期待され、普段の生活で子どもたちに関わる多くの方に知っていただきたいと思いました。
「傾聴と心のケア」では、「傾聴」の始まりであるカール・ロジャーズや、シェンドリンの考え方の歴史を教えていただき、「傾聴」には理論があることを解説していただきました。普段、我々は何気なく患者さんの話を聴いていますが、受容・共感・一致ということを意識し、傾聴していきたいと思いました。講演の最後に、診察終了後に患者側に質問がないか尋ねるだけで満足度があがると聞き、今後、実践していきたいと思いました。
今回の研修会も現地参加178名、web参加451名、合計629名の参加と大変盛況でした。後期の研修会は、7月19日〜20日となります。大勢の方の参加をお待ちしております。
(文責)佐藤 潤一郎
(参考記事)