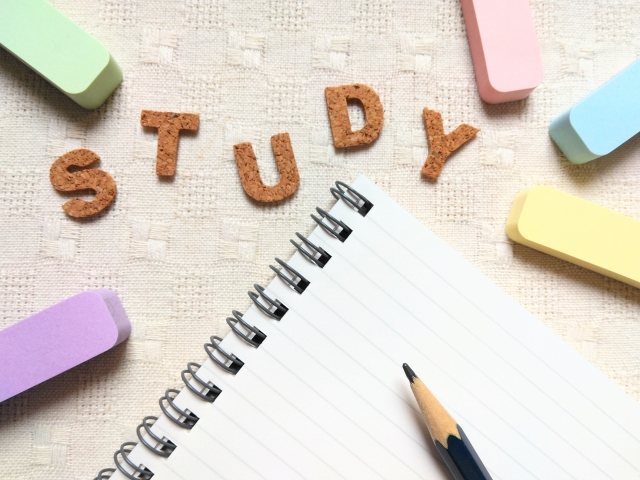第27回「子どもの心」研修会(後期)報告

研修会概要
- 日時:2025年7月19日(土)、20日(日)
- 会場:砂防会館別館利根(東京都千代田区)
- 開催方法:hybrid開催[現地参加/LIVE視聴]
- 参加者:現地参加161名、WEB参加452名、計613名
- 研修会プログラム:第27回「子どもの心」研修会プログラム(PDF)
研修会を終えて
「ICTを活用した子どものつまづきの支援」
認知に困難があっても、テクノロジーの発達のおかげで、子どもの苦手を代替するツールの紹介や自験例を示していだきました。一人一人の認知の仕方が違う中で、苦手さで学習意欲をなくすお子さんには朗報の情報であると感じました。個々の特性を見ながら新しい教育を提供している中邑先生の活動に、今後も注目していきたいと思います。
「小児期逆境体験の早期の予防の可能性」
著書「ACEサバイバー」(ちくま新書)を執筆した講師に講演をお願いしました。講演では、ACEの歴史を紹介していただき、10項目からなるACEスコアと疾病や問題行動などの関連を示していただきました。スコア6点以上が0点より19年早く死亡するという事実は特に驚きでした。ACE問題への対処の仕方も解説していただきましたが、ACEの連鎖の観点からも、子育て支援の必要性・重要性を再認識しました。
「性問題行動のある子どもの理解と支援」
性問題行動へ対する誤解や、健全な性行動と性問題行動の違いなどを解説していただいた。性問題行動は、何らかのニーズがあるというサインと捉え、指導とケアの両方が必要であるということは、我々にとっても大切な視点だと感じた。今回の講演で最も印象に残ったのは、境界線(バウンダリー)の発達の大切さです。健全な境界線の発達を促すために我々は何ができるかを再考させられる講演となりました。
「新型コロナの流行と乳幼児の発達の関連」
講師の発表した論文を執筆するにあたっての背景や先行研究を紹介していただき、研究のデザインを解説していただいた。論文の結果として、3歳時点での明確な発達の遅れは認められなかったが、5歳時点での発達の遅れが平均4.39年であり、5歳前後では両親以外との交流が重要であると考察されていた。この研究は追跡調査されており、今後は学力なども調べてみるとのことでしたので、注目していきたいと思います。
「アタッチメントに基づく親子関係の理解と支援」
アタッチメントの理論をわかりやすく説明していただき、深い学びとなりました。親子関係支援については、「安心感の輪」子育てプログラムを紹介していただきました。「安心感がないと始まらない」というフレーズがとても胸に刺さりました。子どもの安全・安心を与えるためには、養育者にも安全・安心が必要です。孤独な子育てを強いられる現代社会において、「子育て支援」には「親支援」も必要であることを再認識しました。
「子ども虐待対応における医療の役割〜子どもの小さな声を聴こう〜」
子どもの虐待対応に深く関わってこられた木下先生の講演は、「小児科医おせっかいになろう!」「『困った親』は『困っている親』」「カテゴリー診断の早期に紹介」「子どもたちの声なき声を聴く」といった言葉一言一言に大変重みがある内容でした。特に、臨床の現場で、虐待か否か迷うケースでも、腑に落ちない部分があった場合はカテゴリー2・カテゴリー3の段階でも早期に介入・紹介する勇気をもらいました。
一般外来でできる!ゲーム行動症治療の実践
依存症を専門とする精神科の先生に、ゲーム行動症への対応について講演して頂いた。近年の依存症治療の流れとして「harm=害 reduction=減らす」ハーム リダクションといった概念の紹介をして頂いた。ゲーム障害が先行し家庭環境が悪化しているのか(一次性)、生き辛さの問題があり結果としてゲーム障害を誘発しているのか(二次性)の見極めが大切であるが、多くの場合は後者が多い。「ネット問題の綱引き」に巻き込まれず、保護者にも寄り添いながら自己肯定感を高めるプロセスを進めていく姿勢に感銘を受けました。
今回の研修会も現地参加173名、web参加453名、合計626名の参加申込があり大変盛況でした。参加者の先生方には、この研修会をきっかけに、更なる「子どもの心」診療への自己研鑽をしていただきたいと思います。また、参加者でまだ「子どもの心相談医」の登録をされていない先生方は、是非ご登録いただき、自院に「子どもの心相談医」のプレートを掲げ、地域の子どもたちの「子どもの心」診療に携わっていただけることを心よりお願い申し上げます。
(文責)佐藤 潤一郎
(参考記事)