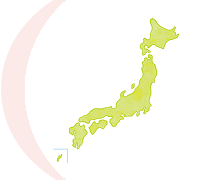目的・事業・会長挨拶
目的
この法人は、小児の保健、医療および福祉の充実、向上を図るための事業を行い、小児の心身の健全な発達に寄与する事を目的とする。
会長挨拶
もとめられる小児科医の行動変容
第35回日本小児科医会総会フォーラムin 埼玉(2024年6月8・9日)が大宮ソニックシティにて小林敏宏埼玉県小児科医会会長のもとで開催され,会期中の2024年度定時社員総会,臨時理事会にて会長へ重任いただきました。短いようで長い2年間です。よろしくお願いいたします。
成育期の子どもたちをどまん中に,その心身の健全な発育・発達に寄与し家庭,大人,社会,国の幸福度をあげ明るい未来をみての平和な社会を作り上げていきたいと思います。会員の皆様には是非ご協力・参加よろしくお願いしたします。
2018年12月成育基本法成立・公布,2019年12月施行されその附則から3年余りの早さで2023年4月にこども家庭庁が開設されました。同時にこども基本法も施行されました。未曽有の少子化の日本の将来を危惧する放置しておけない未解決・未着手の山積みの子どもの問題が後押ししての待ったなしの必然かと考えます。子どもに関係する様々な課題を迅速に解決して行かなければなりません。
我々小児科医の小児医療・保健の現場は従来遅々としていた政策に浸かっていた感が否めません。診療所の中だけでの医業では限界があります。少子化,疾病構造やコロナによる変化に対し我々小児科医も行動変容しなければなりません。
乳幼児健診,学校健診,予防接種など地域の子どもへの健康管理には小児科医のみでは対応できません。内科や他科の先生の協力・協働が必要です。

会長 伊藤 隆一
小児科医は矜持を持って子どもへの医業・小児医療を続けなければなりませんが,他科の先生にすべてを期待することはできません。住む地域で子ども達への医療の格差が生じないようにしなければなりません。産科医や小児科医も偏在する事は事実です。診療所医師の高齢化や医師の働き方改革も重なります。再来年には正常出産も保険診療へ向かう議論が始まりました。出産も小児医療同様集約化に向かうことになります。自分たちの住む自治体で出産ができなくなる危惧があり人口戦略会議に述べられている消滅可能性自治体となります。18~29歳対象の日本人未婚男女400人への民間インターネット調査で「将来子どもは欲しくない」2023年(2020年) では男59%(47.9%),女51.1%(39.6%)。2023年出生数速報値では75万8千人が確定値では72万7千人と予測を大きく下回り2024年には70万人を切る危惧が示されています。人口戦略会議のブラックホール型自治体東京の出生率0.99,韓国人口1/5の1千万人のソウルの出生率は0.55となっています。
右上がりで増える虐待,いじめ,不登校,貧困,自殺,ひとり親,在住外国籍の子ども,母子のメンタルヘルス,発達障害,AYA世代の小児がん,子どもの在宅介護,医療的ケア児,ヤングケアラーなどの対応には多職種連携,行政,議会含む地域での連携,医師会など医師同士の連係が必要,必須です。
8次医療計画で設置が強く進められている「小児医療協議会」へのリーダー的参加もCommunity Pediatricsのかなめとなる地域小児科医会にお願いし,こども大綱に述べられている横,縦のネットワークのネットワークの共助体制の構築,強化を図っていただくようお願いいたします。
2022年12月31日,全国医師数343,275人(274.7人/ 人口10万人)。小児科医数は17,781人となっています。こどもが減っている為,15歳未満人口10万人対医師数は2020 年には1994年の1.8倍となっています。
毎回ですが最後に日本小児科医会入会のお願いです。
医会も日本社会と並行して高齢化が進み会員数の減少が進んでいます。昨今の物価上昇もあり事務局運営費,研修会・総会開催運営費,会議旅費,通信費が高騰しています。今後もWEB研修含む会員の研鑚の場を充実してまいります。
眼科や産婦人科は皆さん学会と同時に医会にも資格保有のため入会が義務とされていますが,子ども育成と同様,次世代の小児医療等の継続につなげる若い小児科医と大学を中心とした勤務医の先生方の入会をお願いいたします。また地域小児科医会のみ所属の先生には日本小児科医会にも同時に入会お願いいたします。
(2024年6月)