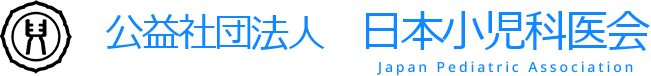当医会の設立の経緯・沿革・会員章の栞(しおり)を掲載しております。
設立の経緯
1979年(昭和54年)1月21日、日本小児科学会理事長は、小児医療全般にわたる医療体制の確立を目指して、同学会社会保険委員会に対し小児医療改善に関する重要事項6項目の諮問をしました。同委員会はこれを受けて検討を重ねた結果、1980年(昭和55年)2月3日「小児医療改善に関する答申」を出しました。その中の第5項目に「全国的小児科医会の結成」があり、これが日本小児科医会の芽生えです。
以後、全国小児科医会連絡会が開催され、1983年(昭和58年)に日本小児科医会設立準備委員会が発足し、1984年(昭和59年)5月18日に日本小児科医会が創立され、初代会長に内藤壽七郎が就任しました。
小児の医療・保健・福祉の向上を目指して積極的な事業展開を行っています。
2000年(平成12年)12月11日、厚生省から正式に社団法人日本小児科医会として認可され、 その後、2011年(平成23年)4月1日に一般社団法人日本小児科医会に移行、2015年(平成27年)に公益社団法人日本小児科医会に移行しております。
沿革
1984年 5月
日本小児科医会 創立(初代会長に内藤壽七郎)
1984年 7月
日本小児科医会 創立記念ニュース発行
1985年 3月
日本小児科医会ニュース 創刊第1号発行
1986年 1月
日本小児科医会会報 創刊
1990年1月
第1回日本小児科医会生涯教育研修会(現総会フォーラム)開催
1990年 6月
WHO予防接種拡大計画担当者のためのワークショップにアドバイザーとして参加
1991年 8月
バングラディシュ小児科学会の要望によりサイクロン被害の子どもたちに20万円寄付
1993年 5月
ラオスのポリオ撲滅協力募金(3年間継続支援)
1995年 1月
阪神・淡路大震災被災地へ特殊ミルク等支援開始とともに義援金を募集
1995年 9月
ベトナムにおけるJICA結核予防接種計画に対して5千ドルの支援(パスツール研究所より感謝状)
1996年 2月
中国雲南省大地震被害救援のため粉ミルク支援
1997年 8月
厚生省児童家庭局母子保健課と共同で“子育て支援ビデオ”を作成
1999年6/7月
第1回「子どもの心」研修会開催 (内閣総理大臣より挨拶)
1999年10月
「子どもの心」相談医登録制度開始
2000年12月
社団法人日本小児科医会として設立・認可
2001年11月
第1回思春期の臨床講習会開催 (厚労省・文科省・日医会長より祝辞)
2003年 1月
福祉医療機構助成事業「タバコから子どもを守ろう」公開講座 及びポスター・リーフレット作成・配布
2004年2月
「子どもとメディア」の問題に対する提言を発表
2004年 3月
健やか親子21平成15年度活動で「子どもの予防接種週間」とし、麻疹ワクチン接種運動を展開(以後定着化)
2004年10月
新潟県中越地震による被災地に見舞金と外来小児科学会作成のPTSD冊子を印刷して送付
2004年10月
小児医療のグランドデザイン(会報28号掲載)
2005年 9月
子どもとメディアの問題に関する啓発ポスター作成・配布
2005年10月
第1回日本小児科医会ワークショップ(現生涯研修セミナー)開催
2007年3月
PTSD啓発冊子「もしもの時に、子どもの心のケアのために」作成
2011年 3月
東日本大震災被災地に紙おむつ・粉ミルク等を贈ると同時に義援金募集開始(5年間事業)
2011年 4月
一般社団法人日本小児科医会として登記
2012年2月
第1回乳幼児学校保健研修会
2012年10月
“小児保健法”ポスター作成・配布
2013年10月
第1回「子どもの心」研修会(導入編)
2013年11月
講演会『成育基本法制定に向けて』-子どもの将来、日本の未来-
2014年 1月
“スマホに子守りをさせないで”ポスター作成・配布
2014年9/11月
豪雨による広島市の土砂災害被災地に有志医会員及び関係団体と合同で282万円を寄付
2015年 4月
公益社団法人日本小児科医会として登記
地域総合小児医療認定医制度開始
“スマホに子守りをさせないで”リーフレット作成・配布
2015年10月
第1回小児救急研修会
2015年11月
日本小児科医会 創立30周年記念式典・祝賀会
第1回地域総合小児医療認定医指導者研修会
第1回家庭看護力醸成セミナー
2015年12月
第1回予防接種・海外渡航合同研修会
2016年3月
本ホームページリニューアル
2016年9月
日本小児科医会が提唱する「成育基本法」についての意見広告を毎日新聞(9月30日朝刊)に掲載
2017年1月
“遊びは子どもの主食です”、“スマホの時間わたしは何を失うか”ポスター作成・配布
2017年3月
熊本地震被災地に有志6団体と合同で250万円を寄付
2017年7月
小児救急電話相談情報収集分析事業実施団体に応募し、選出される。
会員専用ホームページリニューアル
2017年10月
第1回都道府県小児科医会全国会長会議
2017年12月
第1回日本小児科医会記者懇談会
2018月4月
日本小児科医会会報誌査読制度開始
2018年12月
日本小児科医会が提唱する「成育基本法」が成立(国会両院本会議可決)
日本小児科医会 会員章の栞(しおり)
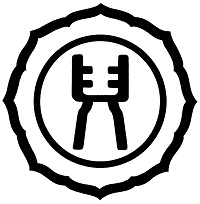
八稜鏡の中央に児の篆字(てんじ)をデザイン化して配置した。
鏡は「手本・模範・戒しめ」をあらわす。
児はここでは「小児科医」のことである。
そこに、子どもの幸福を願って日夜努力している
真摯(しんし)な小児科医の姿をみていただきたい。
それは誇り高く、永遠に光を失うことはない。